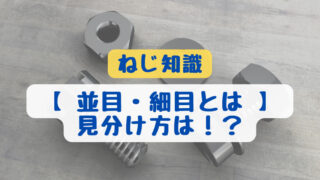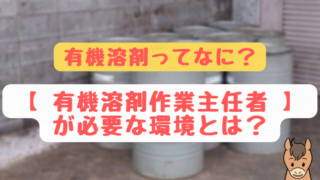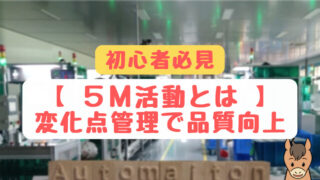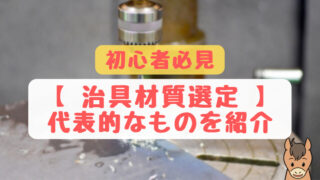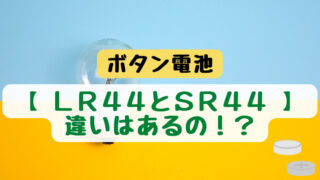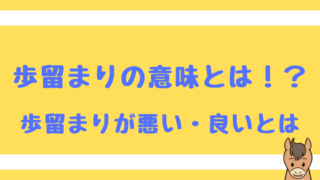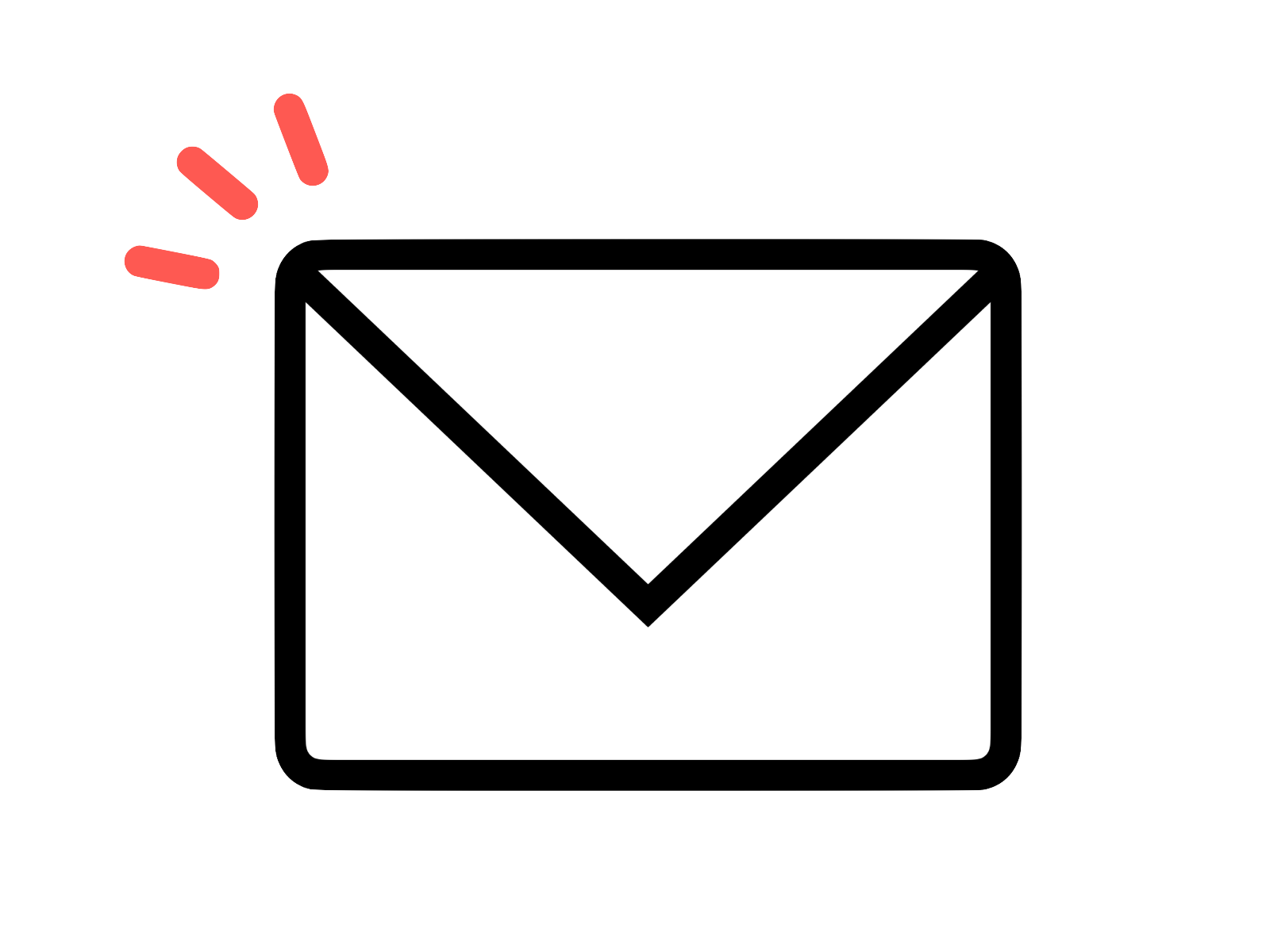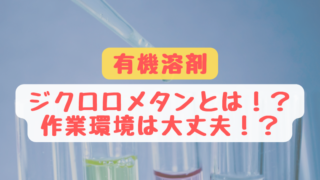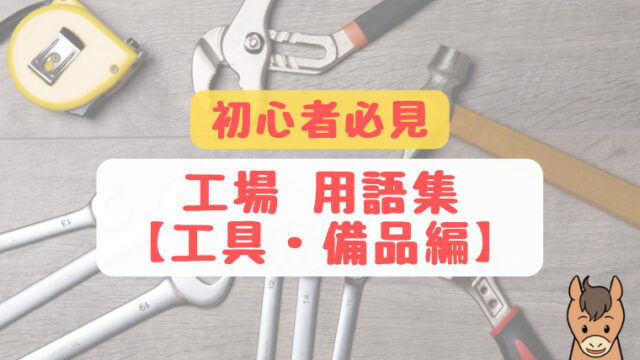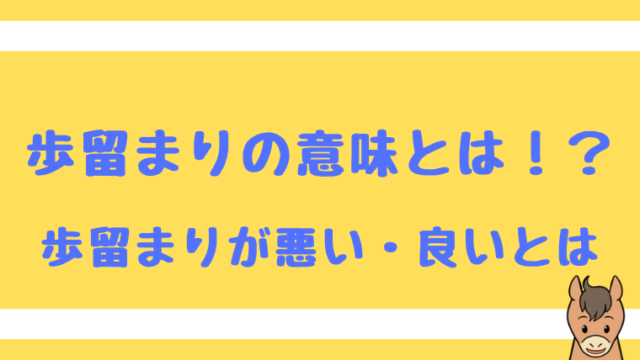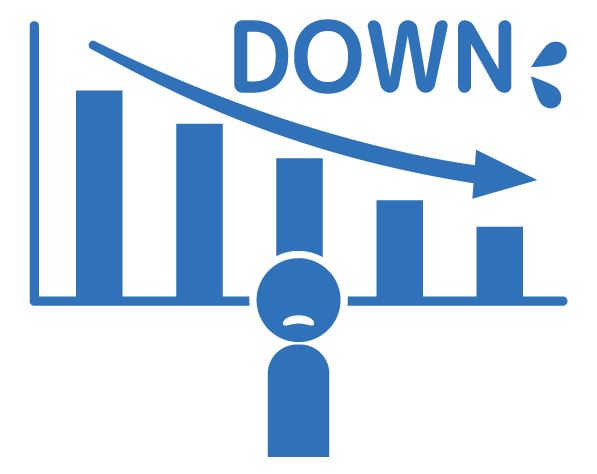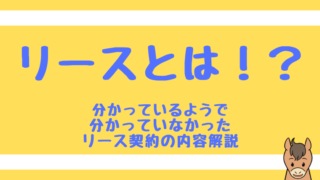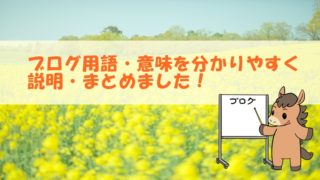今回は治具にどんな材質を使えばいいか迷っているあなたへ
私の選定方法を紹介します。
そもそも治具とは何なのかを知りたい方は先に下記記事をご覧ください。

選定方法は大まかに言うと2つです。
・使用用途
・コスト
みなさまの参考にしていただければ幸いです。
それでは下記に紹介していきます。
使用用途から選定する
材質は、鉄・ステンレス・アルミニウム・真鍮・特殊鋼のように様々あります。
鉄も更に細かく分類するとSS400・S45C・S50C~と無限にあります。
材質がたくさんあることで選定の幅が広がりますが、たくさんありすぎてどれを使用していいかわからなくなります。
そこで私がよく使用している材質をピックアップして紹介します。
まずは、下記一覧でそれぞれの大まかな特徴をご確認ください。
| 鉄系 | ステンレス | アルミニウム | 真鍮 | ※ ダイス鋼/ ハイス鋼 |
樹脂 | |
| 強度・耐摩耗 | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | △ |
| 凹みにくさ | ○ | ○ | ✕ | △ | ◎ | ✕ |
| サビ(腐食) | ✕ | ◎ | △ | △ | △ | ○ |
| 加工性 | ○ | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
※熱処理することを前提として判定。
あくまで大まかに分類したものですので参考程度としてください。
(鉄の中でも加工性が良い快削鋼があったり、アルミニウムの中でも強度を高めたジュラルミンがあったりと、各材料の中でも様々な種類があります。)
各項目について詳しく説明していきます。
強度・耐摩耗
金型のパンチや受けのように何回打ち抜いても耐えられる強度がほしければダイス鋼・ハイス鋼に熱処理したものを使用。
力を加えたときにゆがんだりしなければいいというときはS45CやSS400のような鉄系。
逆に製品を傷つけたくないような環境であればポリアセタールのような樹脂。
のような形で選定します。
凹みにくさ
衝撃を加えたり、何回も荷重をかける環境では凹みにく材質を選定する必要があります。
熱処理をしなければどの材質でも凹む可能性はあるのですが、アルミニウム・真鍮・樹脂は特に凹みやすいです。
ただし、凹みやすいのが必ずしも悪いわけではありません。
製品のガイドや受け治具を考える時、材質がかたいと製品に傷や凹みがつく可能性が出てきます。凹みやすい材質を使用することで、製品への影響を少なくすることができます。
サビ(腐食)
サビない(サビにくい)ものはステンレス・樹脂です。
アルミ・真鍮・熱処理したダイス鋼/ハイス鋼(熱処理前はサビやすい)もサビにくいですが
サビないわけではありません。
鉄系はサビやすいです。
鉄系はサビやすいですが使用をあきらめる必要はありません。
メッキ処理をしてサビを防止することができます。
また、メッキ処理以外にもラッカースプレーでコーティングや塗装をしてサビを防ぐ方法もあります。(ただし、この方法だと塗り方で膜の厚さにばらつきがでるため寸法精度が求められる状況では使用不可)
加工性(切削性)
樹脂、アルミニウム、真鍮、鉄は加工性が良いです。
ステンレス、ダイス鋼/ハイス鋼(熱処理前)は加工性が良くないですが、加工自体は可能です。
ダイス鋼/ハイス鋼は熱処理が入ってしまうと加工が厳しくなってしまうため注意が必要です。

各材料の特徴
鉄系
よく使用するのは【 SS400、S45C 】です。
・SS400:一般的な鉄、安い、加工性も良い。
・S45C:SS400よりも強度がある、値段はSS400より少し高い、熱処理して硬度を上げることができる(ただし反りやすい)。
私の使い分けとしては、硬度が少し欲しいとき・熱処理をして更に硬度を上げたいはS45Cを使用しています。逆に硬度があまり必要ない環境では安いSS400を選定しています。
ステンレス
よく使用するのは【 SUS303 】です。
一般的に広く使用されているステンレスは【 SUS304 】で、これを加工しやすくしたのがSUS303となります。
304と比較してサビにくさや溶接性に劣りますが、加工がしやすいため非常に重宝しています。(溶接が必要な場面ではSUS304の方が向いています。)
ダイス鋼、ハイス鋼
よく使用するのは【 SKD11、SKH51 】です。
どちらも金型部品を製作する時に使用しています。
熱処理をすることで摩耗に強くなり、パンチや受け・摺動(しゅうどう)するような場所によく使用されます。
SKH51のほうがSKD11よりも硬くなりますが、価格が高いです。
どれだけの硬度を求めるかにもよりますが、私はSKD11の方をよく使用します。
非鉄金属(アルミニウム)
よく使用するのは【 A5052、A5056、A2017】です。
アルミニウムは軽く、加工がしやすいのが特徴的です。
A5052は板材、A5056は丸材です。
A5000番系の材料は、成分にマグネシウムが添加されており強度があがったものとなります。
鉄よりも強度が劣りますが、軽さと加工性の良さから使用する場面は多いです。
アルミに強度を求めたいときは A2017(ジュラルミン)を使用します。
更に強度がほしいときは
A2024(超ジュラルミン)
A7075(超々ジュラルミン)
のような材料もあります。
樹脂
よく使用するのは【 ポリアセタール(POM) 】です。
こちらも軽くて、加工しやすいです。
加工性は材質によって異なりますが、精度が少し出にくかったりします。
また、水分を吸いやすい材質や油や薬品に弱い材質もありますので、使用環境に応じて適切な材料を選定する必要があります。
私の場合、製品に傷をつけたくない時は樹脂を使います。
真鍮
よく使用するのは【 C3604 】です。
C3604は快削材で加工性が良いです。
アルミより硬度が欲しい場合は真鍮を使用しています。

高コストにならないか確認する
ダイス鋼/ハイス鋼やステンレスは比較的に高いです。
治具設計ではいかにコストを抑えるかも重要になってきます。
私の場合は、設計仕様的にどうしてもダイス鋼/ハイス鋼やステンレスを使わなければならない場合以外は使いません。
(私の会社は金属加工の会社なのでステンレスの残材がある場合は使ったりします。)
また、サビないようにしたい場合はラッカースプレーや塗装をして安く済ませます。
(たくさん処理をしなければいけなく、人件費のほうがかかりそうな場合はメッキ屋にお願いしています)
取引があるメッキ会社があれば安くお願いするのもひとつの手です。
ここで注意が必要なのはミスミで表面処理した部品を購入する時です。
無電解ニッケルのようなメッキを選択すると結局ステンレスとあまり変わらない値段になることもあるため
価格をよく見ながら選択するようにしましょう。

最後に
今回紹介した内容は本当に一部分です。
材質も特殊鋼、鉄、非鉄金(アルミニウム)、樹脂のようにかなり大まかに紹介してあります。
材料の世界は奥が深いです。
・熱が伝わりやすい・伝わりにくい
・電気を通しやすい
・加工しやすい・しにくい
・溶接しやすい・しにくい
様々あります。
慣れるまでは、インターネットで検索すると材料の特性がすぐ出てくるのでその都度調べるようにしましょう。
注意が必要なのは
大きな力が加わる治具を製作する時です。
材料の強度が不足してると大きな事故につながる可能性もあります。
簡単な治具であれば経験則で選定するのも良いでしょうが、
大きな力が加わる場所の材料選定は強度を調べて計算するようにしましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。